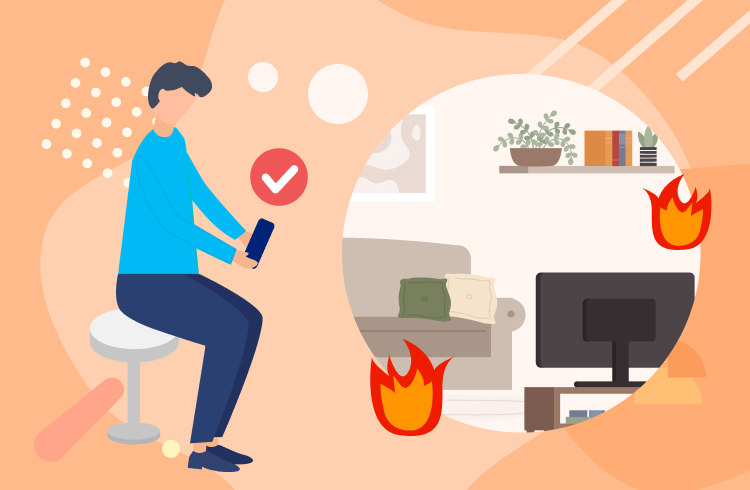このコラムは一般的な情報をご提供するものであり、当サイトの保険のご加入をお勧めするものではありません。
年末調整で失敗しないための保険料控除のチェックポイント
保険は万が一の時の備えとして加入するものですが、年末には"家計の味方"にもなります。生命保険や地震保険に加入していれば、簡単な手続きで節税できる仕組みがあるのです。その方法は会社に書類を提出するだけ。その仕組みを解説しましょう。
保険会社から続々と届く書類を捨てないで
保険会社からの郵送物には興味がないと捨ててしまっていませんか?保険に加入している人であれば、10月になると保険会社からハガキや封筒が届いているはずです。
これらの郵送物は「保険料控除証明書(以下、控除証明書)」と言われるものです。保険料は支払っている間は毎年届くようになっています。
というのも、控除証明書は年末調整や確定申告に必要になる書類だからです。税金を取られそうなイメージがあるかもしれませんが、控除証明書は節税するための書類です。保険料控除は数少ない会社員でもできる節税方法の一つです。まずは捨てずに保管しておきましょう。では、控除証明書を使ってどのように節税できるのか、手続きについてみていきましょう。
控除は税金を安くするキーワード
年末が近づくと会社から「給与所得者の保険料控除申告書(以下、控除申告書)」という書類が配られます。この書類は①生命保険料控除、②地震保険料控除、③小規模企業共済等掛金控除、④社会保険料控除を受けるための書類です。
「控除」というのは、税金を計算する際に課税対象となる「所得」を減らす仕組みです。普段もらっている給与を例に税金の計算方法を見てみましょう。
まず、税引き前の給与そのものを1年分まとめたのが「額面年収」です。額面年収から会社員が認められているみなし経費の性格のある「給与所得控除」を差し引くと「給与所得」となります(STEP1)。さらにここから本人分である「基礎控除」や、扶養家族分である「扶養控除」や「配偶者控除」、その年に支払った社会保険料を差し引ける「社会保険料控除」などを差し引いた「課税所得」を計算します(STEP2)。この「課税所得」に税率をかけると所得税や住民税が決まる仕組みです(STEP3)。
STEP1 額面年収―給与所得控除=給与所得
STEP2 給与所得―各種控除=課税所得
STEP3 課税所得×税率=所得税額
こうしてみると、使える控除をできるだけ積み重ねていくことで課税所得を小さくすることができ、その結果として税額が安くなることがわかります。たとえば、課税所得が300万円の人が、さらに保険料控除を10万円受けられれば課税所得は290万円にまで小さくなります。この課税所得であれば所得税率は10%なので10万円の10%である1万円分所得税が少なくなる計算です(さらに来年支払う住民税も安くなります)。
こうして計算した所得税額が、給与や賞与から差し引かれた源泉税の総額よりも小さくなれば、多く払いすぎた所得税が「還付」されます。12月の給与の手取り額が、いつもの月より多いと感じたなら還付されている可能性が高いです。まさに生命保険料控除や地震保険料控除はSTEP2の各種控除の一種です。会社員のあなたがするのは、控除申告書に必要事項を記入して、控除証明書を添付して会社に提出するだけ。あとは会社が手続きをしてくれます。これでも面倒くさいと思うかもしれませんが、控除を正しく反映させるために必要な手続きなので頑張りましょう。
手続きのミスが意外に多いので気を付けよう
このように使えるなら使いたい保険料控除ですが、がんばって手続きしたのに控除が受けられないとなるともったいない。慣れない手続きでミスも多く出るのも事実です。
たとえば、控除申告書を記入して提出したものの、家に届いた控除証明書の提出を忘れるミス。控除証明書は一般的に10月ごろ届きますが、申告書を提出するのは11~12月。この時間差によって控除証明書を無くしてしまう方も多くいます。
もしかすると、控除証明書なんて届いていない!という人もいるかもしれません。郵便事情で届かなかったということもあるかもしれませんが、引っ越しをしたのに住所変更届を出していない方も多く見らます。保険会社に住所変更をしていなければ、旧住所に送られてしまうので受け取れないことも起こりえます。早めに住所変更届をしておきましょう。
さらに、控除証明書を提出したのに控除されなかった、ということも起こります。よくあるのが、前年以前の古い控除証明書を提出してしまった場合です。有効なのは当年分の控除証明書だけ。提出する際には何年分の控除証明書かよく確認しましょう。
控除証明書が見当たらないなら早めに再発行しよう
こうしたミスで数千円~数万円の節税機会を逃すのはもったいないことです。控除証明書を無くしたり、届いていない!というのであれば、再発行できるので早めに依頼しましょう。手続きはシンプルです。保険加入している保険会社や、加入手続きをした保険代理店に連絡し発行依頼をすればOKです。手続きの際には契約者本人である確認が行われます。証券番号や住所、生年月日などを聞かれることが多いので、事前に用意しておくとスムーズに進みます。
通常は1~2週間で届くはずですが、年末に近づくほど発行依頼が殺到しやすくなります。余裕をもって早めに依頼することが大切です。最近は控除証明書のWeb(電子)発行に対応する保険会社が増えています。利用できるなら。Web発行の方が便利でしょう。
年末調整に間に合わなくても慌てずに
再発行を依頼するのが遅くなってしまった。前年度の控除証明書を使ってしまい控除を受け損ねた、といった時でも慌てる必要はありません。確定申告をすれば払いすぎた税金を取り戻すことが可能です。確定申告と言えば自営業の方がやるものというイメージがあるかもしれません。会社員でも年末調整で控除の申告ができなかったら、確定申告で申告し直すことで正しい税額に修正され還付してもらうことができます。
確定申告の期限は原則2月16日〜3月15日ですが、還付申告の期限は翌年1月1日から5年間です。つまり過去5年分までさかのぼって申告できます。過去に忘れていた控除が数年前のものであっても、まだ取り戻せるかもしれません。
還付申告手続きに必要なのは控除証明書や源泉徴収票です。これらをそろえて申告書に記入して提出します。国税庁の「確定申告書など作成コーナー」やスマホからのe-Taxを使えば、自宅から簡単に申告できます。また、ネットやスマホから申告する場合、マイナポータル連携を設定すれば、控除証明書を電子データとして受け取り活用もできます。PCやスマホを使った申告は過去の申告データも参照でき、とても便利です。
控除を目的に保険加入するのは×
控除で税金が戻るなら、保険にどんどん入った方がお得、と思う方もいるかもしれません。たしかに生命保険料控除や地震保険料控除を申告すれば、所得税や住民税が軽減されます。ところが、控除できる金額には上限があります。
例えば、生命保険料控除の最大控除額は4万円(所得税、住民税は2万8千円)です。生命保険料控除には一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3種類あり、それぞれ最大控除額が4万円です。それぞれの生命保険料控除は年間8万円の保険料を払えば上限に達します。一種類の控除を得るために何十万円も保険料を払っても、控除の恩恵は変わりません。死亡保険、医療保険、年金保険と、3種類の保険料控除を使い分けるならともかく、控除目的で保険にたくさん入るのは控除を得る目的では意味がありません。
保険に加入するのはあくまで「万一の備え」です。まずは必要な保障の種類、必要な保障額をカバーすることを考えましょう。必要以上に保険契約を重ねると、家計を圧迫し、保険料の支払いが重荷になります。控除を得るのは目的ではありません。あくまでおまけと考えて活用しましょう。