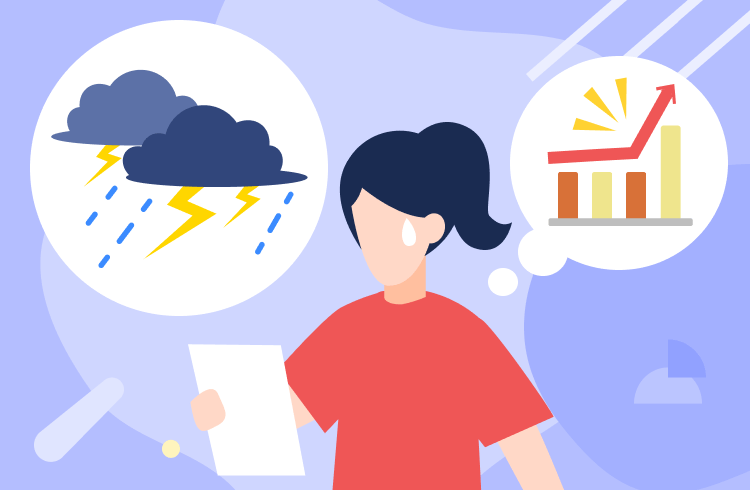このコラムは一般的な情報をご提供するものであり、当サイトの保険のご加入をお勧めするものではありません。
地震保険料控除をお忘れなく
年末・年始になると年末調整、確定申告の手続きをするシーズンに突入します。10月から11月には保険会社各社から「保険料控除証明書」が届きます。また、会社員の方には11月から12月にかけて会社からは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「給与所得者の保険料控除申告書」を渡され提出を求められます。自営業の方であれば、2020年は2月17日から始まる確定申告シーズンに向け、資料の整理を始めるころかもしれません。
生命保険に加入している方であれば「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のいずれか該当する控除を申告します。こうした生命保険料の控除については、一般的によく知られている中、見落とされがちなのが加入している損害保険料の控除の申告です。どのようなものを控除できるのか見てみましょう。
2006年の改正で地震保険料控除に一本化された
2006年まではその年に支払った損害保険料は「損害保険料控除」として申告していました。2006年の税制改正により2007年から「地震保険料控除」が誕生しました。一方で損害保険料控除は廃止されました。つまり、損害保険のうち保険料控除となるのは、原則として地震保険のみとなったということです。
ただ、この改正に際して経過措置が設けられました。以下の条件のすべてに当てはまる損害保険契約であれば「旧長期損害保険料」として引き続き控除することが可能です。
(1)2006年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が2007年1月1日以後のものは除く)
(2)満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
(3)2007年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
地震保険料控除の仕組み
では、地震保険料控除を申告すればどの程度の節税となるのでしょうか。その計算のカギは控除額と、所得税率です。まずは、地震保険料控除がいくら可能なのか見てみましょう。
地震保険料控除額等の計算方法
① 所得税
|
② 住民税
|
このように地震保険料控除の額は所得税、住民税それぞれ異なった計算式で計算します。上限は所得税の計算では5万円、住民税では2万5000円です。地震保険料が年5万円までであれば支払った保険料がそのまま、住民税の計算では支払った保険料の1/2を控除できます。5万円を超えている場合は、一律5万円(住民税2万5000円)です。
旧長期損害保険料に該当する契約がある場合は、上限1万5000円(住民税は上限1万円)を控除することができます。地震保険料控除と旧長期損害保険料控除が両方使える場合は、それぞれ合計して上限5万円(住民税は上限2万5000円)まで控除することが可能です。
地震保険は保険期間5年を限度として長期契約を結ぶことが可能です。2年以上の長期契約の場合、保険期間分の地震保険料を一括払いします。ですから、長期契約となるとまとまった金額の保険料となりますが、保険期間が長くなるほど割引が効きます。たとえば保険期間5年で地震保険料を10万円支払った場合、毎年の地震保険料控除は10万円/5年=2万円/年として控除額を計算します。
税金が安くなり実質保険料が割引に
ここで言う地震保険料控除額がそのまま税金が安くなるわけではありません。この額だけ所得を少なくすることができるというだけです。実際に税金が安くなるのは、この控除額に税率をかけた額となります。
たとえば、地震保険料控除が上限の5万円(住民税2万5000円)利用できるとして、どれだけ税金が安くなるのか計算してみましょう。所得税率が10%の人では所得税が5,000円、住民税は一律10%ですので2,500円、合計7,500円安くなる計算となります。地震保険料控除を活用すれば、これだけ実質の地震保険料が安くなるということです。
上記のように地震保険料が5万円までの人であれば所得税ではそのままの額、住民税は1/2の額が控除額という計算でした。そのため、税金が安くなることによる地震保険料の実質の割引率は所得税率+5%(住民税分)という計算になります。つまり所得税率所得税率5%の人であれば実質10%引き、20%の人であれば実質25%引きで地震保険に加入しているのと同じ計算となります。
木造の一戸建ては地震保険料が高い
地震保険料控除の計算式を見ると効率的に思えるのは、地震保険料が年5万円までの場合です。もしもお住まいがマンションの場合は、年5万円以内に収まる可能性が高いでしょう。マンションは建物分の保険金額が低く抑えられます。さらに、マンションのように鉄筋コンクリートや鉄骨造の建物は地震保険料の単価自体も木造建物に比べ大幅に低いからです。
ただ、マンションにお住まいの方で地震保険に加入している人の割合は高くはありませんが、建物だけでなく家財に対して地震保険をかけたとしても年5万円に収まることが多いでしょう。
一方で、地震保険への加入率が高いのが木造に住んでいる方。マンションに比べリスクが高い分、木造の一戸建てに住んでいる方の地震保険料は高くなりがちです。千葉県、東京都、神奈川県、静岡県は全国で最も地震保険料の単価の高い地域ですが、保険金額1000万円あたり3万8900円となっています。地震保険は火災保険金額の1/2までしかかけることはできないので、火災保険金額が2000万円であれば地震保険金額は1000万円が上限となります。この程度であれば地震保険料が年5万円を超えることはない計算となります。ただし、建物の面積が大きな住宅や、家財保険にも加入すれば年5万円を超えることは十分にあるでしょう。この場合は、どれだけ地震保険料が高くなっても、地震保険料控除額は一律5万円となりますので、上記の実質的な地震保険料の割引率よりも低くなります。
まとめ
最近は地震が頻発し、巨大地震がやってくるのではないかと心配する人も多いのではないでしょうか。地震保険の世帯加入率は年々上昇していますが、2018年度時点で32.2%とまだまだ低い状況です。国としては地震保険への加入率を上げようと地震保険料控除を設けて加入を促しているわけです。高所得な人ほど有利な税制ですが、所得のある人であれば実質割引になる地震保険料控除を活用して地震に備えましょう。