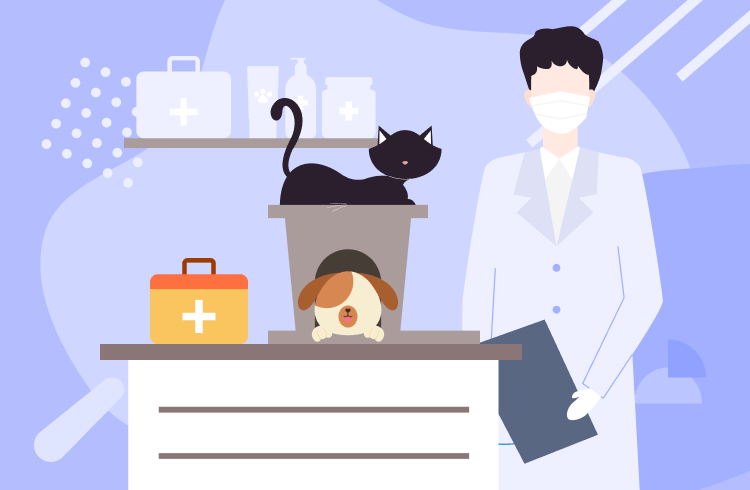
このコラムは一般的な情報をご提供するものであり、当サイトの保険のご加入をお勧めするものではありません。
ペット保険加入前の4つのポイント
先日、わが家の愛犬を近所の公園のドッグランに連れて行きました。小型犬から大型犬まで10頭以上の犬が走り回っていました。うちの子は老犬なので走り回ることもありませんし、犬見知りで他の犬と交わることもほとんどありません。それでも、ワンちゃんたちが元気に遊んでいる雰囲気は好きなようです。いつまでも元気でいてくれればいいですが、残念ながら病気やケガと無縁ではいられません。動物病院で治療をすればお金もかかりますが、飼い主としてはきちんと治療をしてあげたいものです。
ペットには健康保険のような制度はない
私たち人間であれば、健康保険証やマイナンバーカードを病院の窓口で提示すると健康保険を使うことができ、自己負担は治療費の1~3割で済みます。自己負担が高額になれば高額療養費制度という、所得に応じて一定の範囲内の負担に抑える仕組みも用意されています。
ところが、ペットの場合は人間のような公的な健康保険制度はありません。そのため、一般的には動物病院での治療費は全額自己負担となります。また、同じ病気の治療でも動物病院によって請求される治療費が大きく異なることもあります。時には、数万円、数十万円の高額な治療費がかかることもあります。こうした高額な治療費の負担を軽減するために、ペット保険に加入することを検討しましょう。
ペット保険には種類がたくさんあるので、補償内容や保険料にばかり目がいきがちですが、次の4つのポイントも確認した上で比較検討しましょう。
Point1 ペット保険に加入するには加入可能年齢がある
ペット保険には新規に加入できる年齢範囲が決まっています。加入を検討する際には、確認する必要があります。子犬や子猫を迎える際には、多くのペット保険では生後56日(8週間)以上経過していることが加入条件となっています。ペットショップやブリーダーから迎える際には、一般的には56日以上経過しているはずなので多くの場合で問題はないでしょうが、自宅で子犬や子猫が誕生した場合には注意が必要です。
一般的には年齢を重ねるほど病気がちになるので保険への加入ニーズが高まります。ところが、ほぼすべてのペット保険には新規に加入できる上限の年齢が決まっています。犬や猫の場合、早い保険では7歳までと言うように上限が決まっており、高齢になるほど新規加入できる保険会社が減っていきます。最近は10歳を超える高齢の犬や猫も新規加入できるシニアプランを用意している保険会社も登場しています。また、ペットの種類によっても何歳まで加入できるか異なりますので、保険会社に確認しましょう。
Point2 きちんと告知して加入しよう
人間の加入する生命保険と同様に、ペット保険に加入する際にも生年月日や健康状態、治療歴や既往症などの告知が必要です。
ペット保険はペットの種類や、年齢、体重などによって加入の可否や保険料が異なります。ところが、ペットの生年月日がハッキリと分かる場合だけではありません。保護犬のように正確な生年月日や年齢が分からない場合はどうしたらよいのでしょうか。
まずは、譲り受けた時に年齢が分かるかどうか確認しましょう。もしも分からない場合でも、あきらめる必要はありません。その場合は、動物病院に連れていき推定年齢を調べてもらいましょう。多くのペット保険では、推定年齢で告知すれば足りることになっています。推定年齢でも生年月日を記入する必要があるなら、家にやってきた月日(推定年齢に合わせて)などを記入するのでもよいでしょう。
保険会社によって内容は異なりますが、治療歴や既往症についても告知します。ワクチンの接種状況を聞かれる場合もあります。既往症がある場合、病気の種類によっては加入ができないケースもあります。また、該当する病気に関しては補償されないという条件が付く場合もあります。
もしも、告知すべきことを告知しなかったり、ウソの内容を告知した場合、どうなるのでしょうか。保険会社は告知義務違反がないか調査します。もしも、加入時に違反が判明すれば加入を断られます。また、給付金を請求する際には、調査が入ると思っておきましょう。調査の結果、告知義務違反が判明すれば、給付金が支払われないだけでなく、契約自体が解除される可能性もあります。
治療歴や既往症があり加入できるか怪しい状況なら、複数の保険会社に加入申し込みをしてみましょう。告知すべき項目は保険会社によって異なりますし、同じ告知内容でも保険会社によって審査の結果が異なります。普通に加入できる保険会社が見つかるかもしれません。また、保険会社によっては条件付きで加入を認めるという結果がでるかもしれません。複数の会社からの回答を比較した上で、より条件のよい会社を見つけるとよいでしょう。
Point3 何歳まで更新できるか条件を確認しよう
一般的にペット保険は保険期間が1年で、保険期間終了後は更新して継続することができます。原則として、ペット保険は一度加入したら、更新をしていく限りは何歳まででも続けることができます。
ただし、注意したい事項が2点あります。まず一つ目は、保険会社によって、更新に条件がつく保険会社があることです。更新時も加入時の条件のままの継続できる保険会社も多くあります。ところが、中には更新を断られたり、病歴によって特定の病気が補償対象外となる保険会社もあります。加入する前に、更新時の条件についても確認しておきましょう。
2点目は、保険期間を更新できたとしても、保険を続けられないことがあることです。一般的にペット保険は高齢になるほど保険料が高くなります。そのため、高齢期になると保険料負担に耐えられなくなる可能性があります。多くの保険会社で年齢ごとの保険料表が開示されています。長生きすることを前提として、保険加入の前に高齢期の保険料水準も確認しておきましょう。
Point4 補償対象外の病気を確認しておこう
ペット保険には補償対象外となる病気が定められていることが一般的です。病気になって保険金を請求しても出ないとなると困ります。ペット保険に加入する前に、どのような病気が補償対象外となっているか確認しておきましょう。
ペット保険を検討する際には「重要事項説明書」や「保険約款」を確認するようにしましょう。保険約款の「保険金をお支払いできない場合」の内容を確認すると、補償対象外になる病気が列挙されているケースが多いようです。確認できない場合は、保険会社のホームページでよくある質問(FAQ)を見ると確認できる場合もあります。
保険会社によって異なりますが、補償対象外とされる病気には「歯周病」「椎間板ヘルニア」「膝蓋骨脱臼(パテラ)」「腎不全」「尿路結石」「てんかん」と言ったものが列挙されているケースが多く見られます。補償されない病気があったとしても、それぞれの病気は犬か猫か、種類、小型か中型か大型か、によって、なりやすさに違いがあります。もしも、補償されない病気が、なりにくいものであれば気にする必要はないでしょう。
もう一点注意したいのは、契約後に発症した先天性・遺伝性疾患も補償対象外としている保険会社もあることです。保険契約時や待機期間中に発症していなければ補償対象とする保険会社もあります。ペットの種類によっては、遺伝的な疾患が高確率で発症します。できるだけ、契約後の発症については補償してくれる保険会社を選びましょう。
ペット保険は種類がたくさんあるので、選ぶのは簡単ではありません。また、ペット保険は、獣医さんや周囲の知人からの情報で判断し選ぶ人も多いでしょう。ただ、高齢になっても長期にわたり続けていくなら、補償内容や保険料をしっかり比較して選ぶのは当然です。さらに、加入しているのに保険金が出ない、ということにならないよう上記4つのポイントを必ず確認してから加入するようにしましょう。





