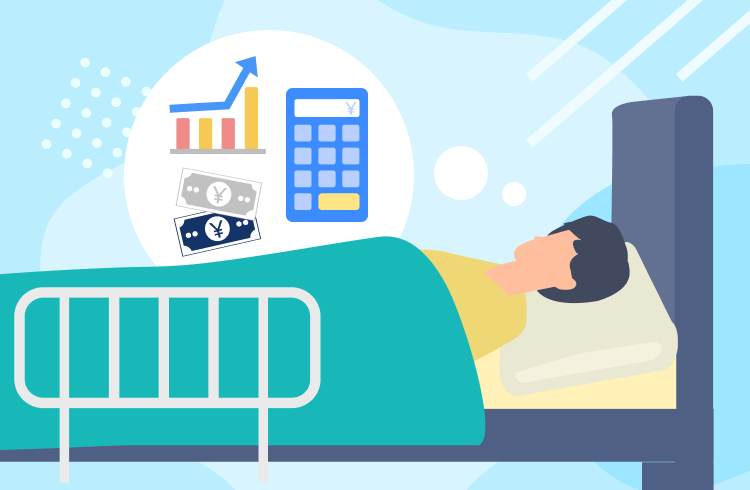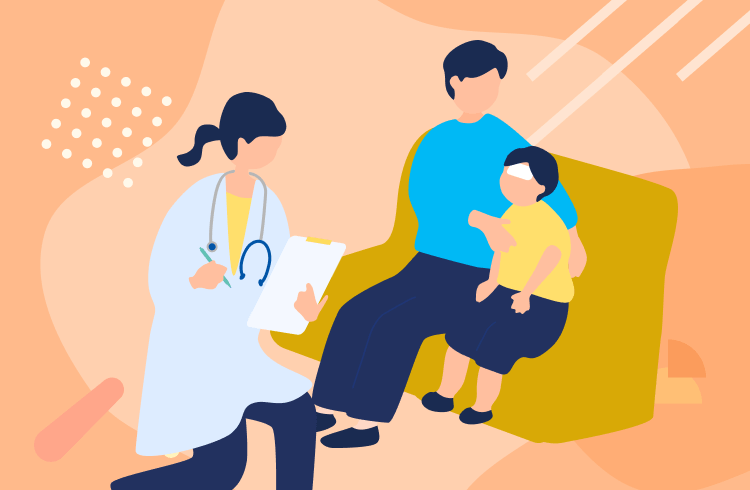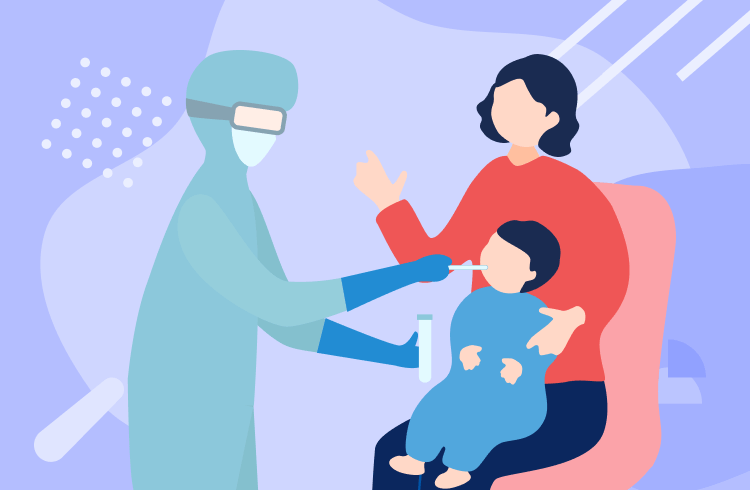
このコラムは一般的な情報をご提供するものであり、当サイトの保険のご加入をお勧めするものではありません。
子供や赤ちゃんの急な高熱、どうすればいい?原因や対処法を知って冷静に対応しよう
「朝は元気だったのに幼稚園や学校から帰って元気がないと思ったら、あっという間に40度近い高熱が出た......。」このような経験に覚えがある親は少なくないでしょう。「しばらく様子を見るべきか」「すぐに医療機関に連れて行くか」など親としては悩んでしまうことも多いのではないでしょうか。
高熱で苦しそうな子供や赤ちゃんを見ることは、親も心が痛みますが、できるだけ落ち着いて様子を見てあげることが大切です。場合によっては、放っておいてはいけない病気の可能性もあります。本記事では、子供の発熱の原因や受診の目安、家での対処法などについて解説します。
子供や赤ちゃんの高熱の原因と症状
子供や赤ちゃんは、急に高熱を出すことがありますが、基本的に発熱はウィルスや細菌などから体を守ろうとする正常な反応といわれています。ここでは、発熱の原因や症状について知識を再確認していきましょう。
子供や赤ちゃんの高熱とは
そもそも「高熱」と呼ぶのは何度からなのでしょうか。元気なときの平熱は、子供や赤ちゃんによって異なるため、個々の平熱に応じた判断が必要ですが、目安となるのは38度です。こども家庭庁が公表している「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)」によると、子供や赤ちゃんに38度以上の発熱が見られる場合、次のような対応が推奨されています。
・保育園にいる場合は親に連絡をするのが望ましい
・登園前であれば、登園を控えるのが望ましい
また発熱の程度だけではなく、例えば「元気がなく機嫌が悪い」「咳で眠れず目覚める」「食欲がなく水分がとれない」など子供や赤ちゃんの状態に合わせた柔軟な判断が必要です。ただし「高熱が出た」という判断は、38度を目安にしておくとよいでしょう。なお生後3ヵ月未満児で38度以上の発熱がある場合は、至急受診が必要と考えられています。
参考:こども家庭庁「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/cd6e454e/20231010_policies_hoiku_25.pdf
高熱の原因
子供や赤ちゃんの高熱の原因の多くは、ウィルスによる感染症です。人の体は、ウィルスや細菌など外部からの病原体や異物が体内に侵入すると白血球が反応し、これらの異物を撃退しようとします。白血球は、平熱よりも高い温度で働くことから体温が上昇するというわけです。ウィルスや細菌への感染は、以下のように経路が多岐にわたります。
・飛沫感染
・空気感染
・接触感染
・経口感染
・血液媒介感染
・蚊による媒介感染 など
例えば幼稚園や学校でウィルス感染している人の咳やくしゃみ、会話、おもちゃを口に入れたり、遊具をなめたり、病原体の付着した手で口、鼻または眼をさわったりすることでも感染する可能性があります。幼稚園や学校以外でも、公園、習い事、プールなどさまざまな感染経路のなかで過ごしているため、ウィルス感染症を起こして発熱することも自然に多くなる傾向です。
高熱が出たときの症状
高熱が出たときの症状は、子供や赤ちゃんによってもさまざまです。例えば白血球の反応によって体が熱を上げようとするために手足が冷たくなったり、ブルブルと震える「悪寒」が生じたりする場合があります。また「熱せん妄(ねつせんもう)」といって一時的に意味が分からないことをいったり、普段とは違う行動をとったりすることも少なくありません。
通常は短時間で普通の状態に戻る ため、まずは冷静になって様子を見てあげましょう。
高熱が出たときの対応
子供や赤ちゃんが高熱を出す心配ですが、発熱以外の症状が見られない場合は基本的に自宅でケアすることになります。親が家庭でできる対処法を把握しておき、落ち着いて対応してあげましょう。
子供や赤ちゃんの顔色・意識を確認する
まずは「顔色が悪くないか」「意識ははっきりしているか」を確認しましょう。熱のせいで顔が赤らんでいたり、苦しそうであったりすることはありますが、顔色がよく意識がはっきりしている場合やけいれんもない場合は、すぐに受診する必要はありません。顔色が青白い、唇が紫色になる、意識が朦朧としているなどの場合、すぐに医師の診察を受けてください。
安静にさせる
高熱時には体力を温存するため、無理な活動を控え、安静にすることが推奨されます。ゆっくり休む環境を整えて、体の回復に専念しましょう。
環境調節する
手足の冷えや震えがある場合は、部屋の温度を上げることも大切です。熱が上がりきると、逆に手足が温かくなるため、汗をかきすぎないように温度を下げたり、薄着にさせたりするなど涼しい状態にしてあげましょう。適切な室内環境の目安は、室温が夏場で26~28度、冬場は20~23度、外気温との差が2~5度とされています。1時間に1回は換気し、湿度は高め に保つことが重要です。
クーリング
高熱が出ている場合はクーリングを行いましょう。首やわきの下、足のつけ根など大きな血管が通る部分を冷やします。ただし子供が嫌がる場合は、無理に行わないほうがよいでしょう。その場合は、室温や着るもの、氷枕などで温度調節をします。ただし、体が冷えすぎないように注意が必要です。
水分補給する
発熱時は汗をかきやすく、脱水症状になりやすいのでこまめに水分補給をさせてあげましょう。飲料水のほか、経口補水液、湯冷まし、お茶などでも問題ありません。吐き気がない場合は、本人が飲みたいだけ飲ませてあげて大丈夫です。
着替えさせる
体が熱を上げようとしているときは、あまり汗をかきません。しかし病原体を撃退し、発熱の必要がなくなれば体温を下げるために汗をかきます。発熱により汗をかいたら、乾いた衣服に着替えさせます。これにより体温調節がしやすくなります。また、衣服は軽めで通気性の良い素材を選び、熱がこもらないようにすることが重要です。
解熱剤を与える
ここまで説明した対処法をとっても高熱でつらそうな場合は、解熱剤を与えることも選択肢の一つです。使用する際は、医師の指示に従い適切なタイミングと用量で与えることが重要です。特に小さな子供の場合、年齢や体重に応じた薬を選ぶ必要があります。解熱剤で病気そのものを治すことはできませんが、高熱による寝苦しさや倦怠感を和らげることが期待できます。ただし、熱が出ること自体は病気と闘う身体の反応であるため、無理に下げる必要はありません。解熱剤の使用にあたっては、必ず用法・用量を守りましょう。
受診する
高熱が続く場合や顔色が悪い、意識が朦朧としている、呼吸が苦しそう、発疹や痙攣などの症状が見られる場合は、早めに医師の診察を受けることが必要です。また、発熱が数日間続く場合や熱が引いても体調が改善しない場合も同様です。
受診のタイミング
風邪などのウィルス感染症であれば通常3日程度で発熱が治まることが多い傾向です。4日以上発熱が続く場合は、医療機関で受診するとよいでしょう。受診の際には、朝、昼、晩の体温の変化、解熱剤を飲んだあとの体温の変化を伝えると診断に役立つといわれています。体温を測った時間や温度、薬の服用時間など記録しておくのがおすすめです。
迷ったときには「こども医療でんわ相談」
子供や赤ちゃんの高熱への対処や医療機関への受診に迷う場合は「こども医療でんわ相談 ♯8000」を利用する方法もあります。これは、医療機関が閉まっている休日や夜間に子供や赤ちゃんの発熱やケガなどで「どのように対処したらよいのか」「受診したほうがよいのか」など判断に迷った際に、小児科医師や看護師に電話で相談できる国のサービスです。
全国統一の短縮番号「♯8000」をプッシュすれば居住地の都道府県の相談窓口に自動転送されるため、子供の症状を伝え、適切な対処法などアドバイスを受けましょう。
子供や赤ちゃんの高熱、予防はできる?
ここまでは、子供や赤ちゃんの高熱の原因や感染経路について解説しましたが、病原体は体の表面に付着しただけで感染するわけではありません。多くの場合は、病原体の付着した手で口や鼻、眼をさわり体内に病原体が侵入することで感染が成立します。そのため普段の生活管理をきちんと行うことで感染リスクを抑えることが可能です。
子供が家に帰ったら、「手洗い・うがいをしっかりと行う」「入浴で全身をしっかりと洗う」「着ていた服はきちんと洗濯する」などで病原体を体内に寄せ付けないようにしましょう。また体の抵抗力を高めるために、栄養バランスのとれた食事をとったり十分な睡眠をとったりすることも大切です。これらの生活管理は子供一人ではできません。親が常に子供を見守ってあげるようにしましょう。
子供や赤ちゃんが高熱を出したときは慌てず冷静に対応を
子供や赤ちゃんの高熱の主な原因は、ウィルス感染に対する体の反応です。一般的には、3日程度で自然に治ります。まずは、子供や赤ちゃんの顔色や意識を確認し発熱以外の症状が見られないようであれば安静に寝かせてあげましょう。しかし「高熱が4日以上続く」「解熱剤が効かない」「顔色が悪い」といった場合は、医療機関を受診しウィルス感染以外の可能性を調べてもらうことも大切です。
子供や赤ちゃんが急に高熱を出すと親のほうが慌ててしまいがちですが、高熱からの回復には親が冷静に子供や赤ちゃんを見守り、適切な対処や生活管理をしてあげることが子供や赤ちゃんの安心感や抵抗力アップにつながります。親が冷静に対応できるように、医療保険で少しの備えをしておくのもおすすめです。
PayPayほけんの「これだけ医療」は、24時間365日電話で「病気やケガの悩み」や「緊急時の対応」を相談できるため、冷静な対応へのアドバイスが可能です。気になる症状がある場合など、利用してみてはいかがでしょうか。