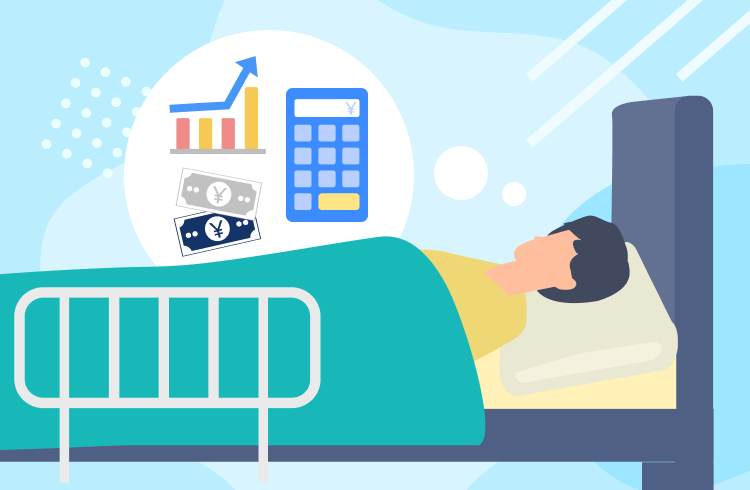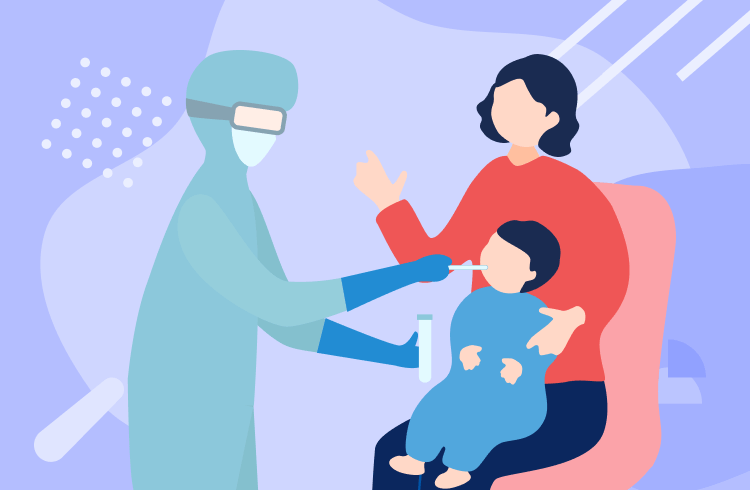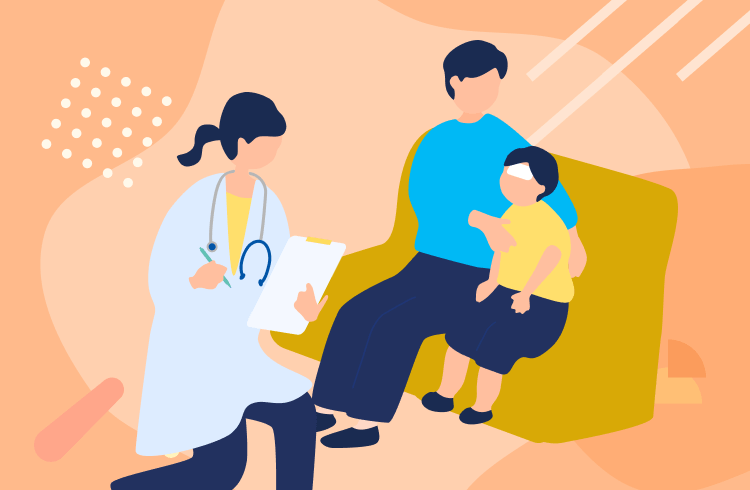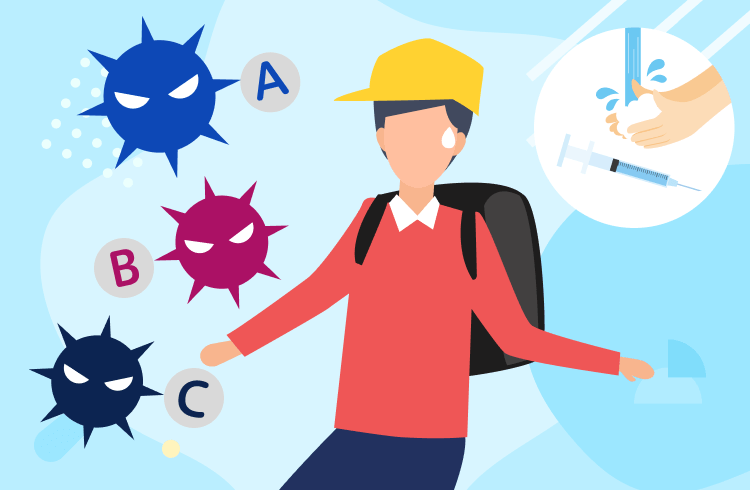
このコラムは一般的な情報をご提供するものであり、当サイトの保険のご加入をお勧めするものではありません。
子供のインフルエンザ予防どうする?家庭での対処法や受診の目安、ワクチンの助成などについて解説
インフルエンザ流行のニュースを聞くと「子供が感染しないか気が気でない」という親御さんは多いのではないでしょうか。インフルエンザは感染力が強く、特に乳幼児期などは重症化リスクもあります。親は子供の感染予防に努め、インフルエンザの疑いがある場合は適切に対処してあげたいものです。
本記事では、インフルエンザの予防法や感染した場合の症状や観察方法、家庭での対処法などについて解説します。
インフルエンザとは?
インフルエンザは「インフルエンザウイルス」という病原体に感染することによって起こる病気です。冬に流行しやすく主な感染経路は「飛沫感染」で、鼻やのどなどについたインフルエンザウイルスが咳やくしゃみで飛散されて広がりやすい特徴があります。
のどの痛みや鼻水、くしゃみ、咳などの症状もあるため、普通の風邪と間違う場合もありますが、インフルエンザは重症化しやすいため、症状をしっかりと観察することが大切です。
インフルエンザと疑う症状
インフルエンザは、普通の風邪にも見られる、のどの痛みや鼻水、くしゃみ、咳などの症状に加え、38度以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、食欲不振、倦怠感などの全身症状が比較的急速に現れる傾向です。また吐き気や嘔吐(おうと)、下痢などの胃腸症状が現れることもあります。合併症として気管支炎や肺炎など、基礎疾患の悪化を引き起こすこともあるため、注意が必要です。
インフルエンザの種類
インフルエンザウイルスは、大別すると「A型」「B型」「C型」の3種類に分けられます。
・A型
前述したような高熱や頭痛、関節痛、筋肉痛、食欲不振、倦怠感などの全身症状が現れ、3種類のなかで最も強いタイプです。通常は、一度感染すると体内に免疫が作られますが、変異しやすいウィルスのため、すでに獲得した免疫が機能しにくい特徴があります。
・B型
A型に比べると症状がやや軽いことが多いですが、発熱、咳、喉の痛み、筋肉痛など典型的なインフルエンザの症状が見られます。散発的あるいは局地的な流行を起こし、A型のように大流行することは少ないと考えられています。
・C型
C型は他の2つに比べて、感染するケースが少なく、通常は軽症で済むことが多いです。発熱や軽い咳が見られることが多く、通常は風邪に似た症状で、感染してもインフルエンザと気づかないことも少なくありません。いったん免疫を獲得すると終生その免疫が持続すると考えられており、かかるのは4歳以下の幼児が多い傾向です。
インフルエンザの予防法
子供がインフルエンザで重症化しないためには、感染しないことが第一です。生活管理やワクチンなど、親が積極的に予防対策を講じてあげましょう。インフルエンザ予防には、主に以下のような方法が効果的です。飛沫感染しやすいことを考えると、子供だけでなく家族全員で予防に努めることも求められます。
うがい・手洗い
ウィルスが皮ふに付着するだけでは感染しませんが、ウィルスが付着した手指を介して体内に入れば感染する可能性が高まります。そのため外出先から帰宅後、うがいや流水・石鹸による手洗いをして手指など体についたインフルエンザウイルスをしっかりと除去しましょう。アルコール製剤による手指衛生も有効です。
流行しているときは人混みを避ける
小さい子供がいる親は、自分の外出時、一緒に連れていかないといけない場合も多いかもしれません。しかしインフルエンザが流行しているときは、できる限り人混みや繁華街への外出を控えることが大切です。やむを得ず外出して人混みに入る可能性がある場合は、「子連れで行かない」「不織布製マスクを着用する」「帰宅後は子供に接触する前にウィルスを洗い流す」などを心がけましょう。
規則正しい生活リズムをつくる
免疫や体の抵抗力が落ちているとインフルエンザウイルスに感染しやすくなります。体調や生活環境の管理に努めて体の抵抗力を高めましょう。そのためには、睡眠や食事をはじめとした規則正しい生活リズムを作ることが大切です。
ワクチンを接種する
生後6ヵ月以上の子供であれば、インフルエンザが流行する前にワクチンを接種しておくことで感染リスクの低減が期待できます。とはいえ前述したようにインフルエンザウイルスは、変異を繰り返すため、ワクチンを接種すれば絶対にかからないわけではありません。それでもインフルエンザ発病後の重症化防止に効果があると考えられているため、接種を検討するのもよいでしょう。
厚生労働省が推奨している13歳未満の子供の接種量は、以下のとおりです。
・6ヵ月以上3歳未満:1回0.25mL 2回接種
・3歳以上13歳未満:1回0.5mL 2回接種
ただし基礎疾患の有無など個人の状況によって接種量が変わる場合もあります。ワクチン接種が不安な場合は、かかりつけ医に相談してみましょう。
インフルエンザワクチンには助成がある?
ワクチン接種は、病気の予防であり治療ではないため、公的医療保険が適用されません。接種費用は、医療機関や投与量によっても異なり1回2,500~5,000円程度と幅があり、原則全額自己負担となります。つまり子供の場合は、2回で5,000~1万円程度が目安です。ただし一部の自治体では、子供がインフルエンザワクチンを接種する場合の費用を助成しています。
対象年齢や助成額、助成条件は自治体によって異なるため、居住している自治体に確認してみましょう。助成がない自治体も多いため、接種を受ける前に必ず確認してください。
もしもインフルエンザにかかったら?家庭での対処法
インフルエンザワクチンを接種してもインフルエンザにかかる場合はあります。インフルエンザにかかってもすぐに受診する必要はありませんが、重症化させないためにも家庭で適切な対処をしてあげましょう。
家庭での観察ポイント
インフルエンザは、3~4日間の発熱が続いたあとに自然に治るといわれています。しかし場合によっては、合併症を引き起こす可能性があるため、まずは観察が第一です。主に以下のような全身の状態を観察することが求められます。
・体温
・顔色
・子供の機嫌
・咳
・鼻水
・頭痛
・関節痛
・倦怠感
・嘔吐(おうと)
・便の状態
・尿の量・色
・食欲 など
なお熱があるときは、朝・昼・夕方・夜(深夜)と1日4回測り、前回測定時からの熱の上がり方をチェックしておくことも大切です。
安静にさせる
体の抵抗力が下がっているため、安静にさせてあげましょう。外出は避け、室内で静かに過ごさせることが重要です。
環境調節する
発熱すると手足の冷えや震えを起こしやすくなります。部屋の温度を上げたり、衣服を1枚多く着させたりするなど体を温めてあげましょう。一方、暖房で部屋を暖めすぎると室内が乾燥し、余計につらくなる場合もあります。定期的に換気し、適度な湿度を保つ工夫をしましょう。適切な室内環境の目安は、室温が夏場で26~28度、冬場は20~23度、外気温との差が2~5度とされています。
クーリング
高熱がある場合は、首のつけ根・わきの下・足の付け根を冷たいタオルでふいたり、氷枕をあてたりして子供が気持ちいいと感じるように冷やしてあげましょう。なお子供が嫌がる場合は、無理に行わなくて構いません。
水分補給する
高熱があると脱水症状を起こすこともあるため、こまめに水分補給をさせてあげましょう。飲料水のほか、経口補水液、湯ざまし、麦茶など子供が飲みやすいものを与えます。
着替えさせる
熱が下がりだしたら汗をかきやすくなります。気持ちよく寝られるように、蒸しタオルで体をふいたり、こまめに着替えさせたりしてあげましょう。
解熱剤には注意
高熱で苦しんでいる子供を見ることは、親にとっても心苦しいものです。しかし、むやみに解熱剤を与えることは避けましょう。発熱は、体がインフルエンザウイルスと戦っている証拠であり、薬で熱を下げることは体の抵抗力を下げることになりかねません。また市販の解熱剤のなかには、インフルエンザのときには使えないものもあります。
どうしても高熱でつらそうな場合は、かかりつけ医などに相談することをおすすめします。
受診するべきタイミング
以下のような症状が見られる場合は、かかりつけ医などを受診しましょう。
・けいれんしている
・異常にぼんやりしている、呼びかけをしても反応が弱い
・意味不明なことを言う、走り回るなどいつもと違う異常な言動がある
・顔色が悪い、唇が紫色をしている
・呼吸が苦しそう
・水分がとれない
・水分をとっているが、尿が濃いまたは量が減る
・嘔吐や下痢が頻繁にある
・ぐったりとしている
受診したら医師に伝えること
受診する際は、診断に役立つように以下のことを伝えましょう。
・発熱がいつから起こり、その後どのように経過しているか
・機嫌、咳、鼻水、便の状態、嘔吐(おうと)などの症状
・水分、食事はとれているか
・尿の様子
・薬を飲んだ場合は、その種類と飲んだ時期
これらの情報を適切に伝えるためにも家庭での観察は大切です。
症状が和らいだら登園・登校はできる?
学校保健安全法およびこども家庭庁の「保育所における感染症対策ガイドライン」では、インフルエンザにかかった場合の登校・登園の目安を「発症後5日を経過し、かつ熱が下がって2日(幼児は3日)経過していること」としています。登校・登園時には、医師による「意見書(治癒証明書)」などの提出が必要になる場合が多いため、保育園や学校に確認しておきましょう
インフルエンザは予防・観察が第一
インフルエンザは、通常3~4日で発熱が治まり、1週間程度で全身症状が自然に回復するといわれています。しかし咳やくしゃみなどで飛沫感染しやすく感染すると全身につらい症状が出るため、できるだけ感染を防ぐことが第一です。万一インフルエンザにかかると免疫や抵抗力の弱い子供は、重症化や合併症の可能性もあるため、しっかりと観察するようにしましょう。
受診時に適切な情報を医師に伝えるためにも、今回解説した観察ポイントを参考に親がしっかりと見守ってあげることが大切です。PayPayほけんの「これだけ医療」で少しの備えをしておくと、親の安心にもつながります。親が落ち着いて対応することで子供にも安心が伝わり、回復に向かいやすくなるのではないでしょうか。